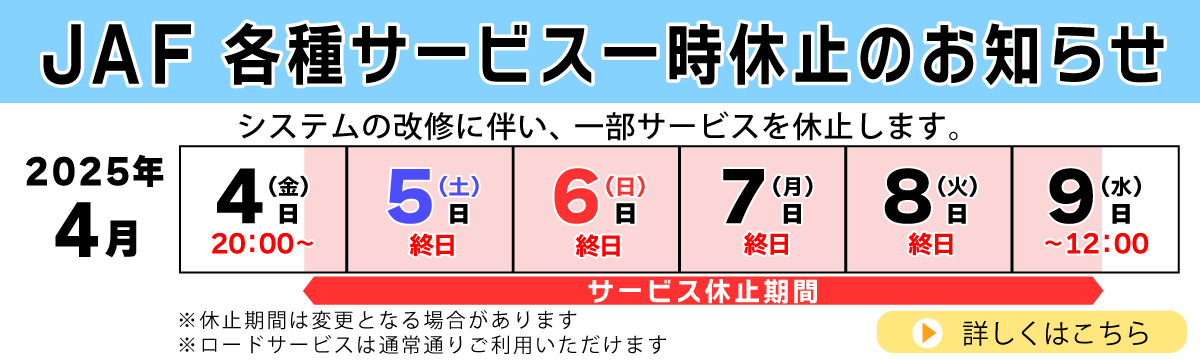3県合同企画「眺めて富士山、気分は北斎」
~富士山を望み、JAF神奈川・山梨・静岡を知る~
2024年7月に新紙幣の造幣が開始、千円札に浮世絵師:葛飾北斎が描いた木版画「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」が初めて採用されました。それに伴い、今回は富嶽三十六景にちなんだ富士山の絶景スポットに焦点を当てたJAFアプリクーポン企画を実施します。現地に訪れた際は、ぜひ富嶽三十六景が描かれた場所から現在の様子を写真に収めてみてください。神奈川県

相州箱根湖水 (そうしゅうはこねこすい)
現在の神奈川県足柄下郡箱根町。箱根湖水は神奈川県足柄下郡に位置する芦ノ湖のことを指す。富士をはさみ左側に見える山は三国山、右側の山は駒ヶ岳であるとみられる。波ひとつない湖面が広がり、湖畔のほとりには杉に囲まれた箱根神社がひっそりと佇んでいる。人物はおらずきわめて静寂な風景が広がる。構図を見ると、横に平たい形で様式化された霞雲と、画面の所々に縦に勢いよく生えた杉の木々とが、画面に縦と横の一定のリズムを生んでいる。(引用:東京富士美術館収蔵品データベース)

相州江の嶌 (そうしゅうえのしま)
現在の神奈川県 藤沢・鎌倉。神奈川県藤沢市に位置する江の島は当時も人気の観光名所であった。現在は橋が架かっているが、当時は本図のように干潮時に現れた砂州を歩いて江の島へ渡っていた。限られた時間の中で江の島の弁財天詣でに急ぐ人々の動きが伝わってくる。また渡った先には大きな石灯籠が見え、そこが参道の入口であることが分かる。参道脇にはすでに店が軒を連ねており、ここに多くの人が訪れていたことを窺わせる。砂州の両側に寄せる波の点描表現も面白い。(引用:東京富士美術館収蔵品データベース)
山梨県

甲州三坂水面 (こうしゅうみさかすいめん)
現在の山梨県笛吹市。現在の山梨県笛吹市に位置する御坂(三坂)からみる河口湖と富士の風景である。中央には赤茶けた山肌をあらわにした夏の富士が描かれている。またここから見る富士の姿は、河口湖の湖面に反射して逆さに見えることから「逆さ富士」としても有名である。ここでも波ひとつない湖面に富士の姿が映し出されている。しかし、湖面に映し出されているのは雪をかぶった冬の富士であり、そこには現実ではありえない虚構の風景が広がっている。(引用:東京富士美術館収蔵品データベース)

甲州石班沢 (こうしゅうかじかざわ)
現在の山梨県南巨摩郡。海の断崖で漁をする姿かと見紛うほど、迫り出した岩と波しぶきが目に止まる。描かれた場所は、富士山北西部を流れる笛吹川と釜無川が合流し富士川となる地点、鰍沢(現在の山梨県南巨摩郡)付近とみられる。漁をする父と魚籠を覗き込む息子、それを見下ろす富士の姿、三者三様の光景が画面を飽きさせないものにしている。富士の山容と、突き出た岩と漁師、そして漁師から放たれた網とが三角の相似をなしているのも面白い。(引用:東京富士美術館収蔵品データベース)
JAFアプリクーポン実施施設
静岡県

凱風快晴 (がいふうかいせい)
現在の静岡県富士市。冨嶽三十六景シリーズを代表する作品。画題にある「凱風」とは南風のこと。「赤富士」とも称されるこの情景は、夏から秋にかけての早朝にかぎり見られるという。諸説はあるが、右側に寄せられた構図は左側(東)からの光を意識しているとも感じられ、河口湖付近から富士の北側を捉えたと思われる。秋を予感させる鰯雲の中に悠然とそびえるその偉容は、富士を形象化した作品の中でも唯一無二の逸品といえよう。(引用:東京富士美術館収蔵品データベース)
JAFアプリクーポン実施施設

駿州江尻 (すんしゅうえじり)
現在の静岡県静岡市清水区。江尻は清水港に隣接した東海道の宿駅で、現在の静岡県静岡市清水区にあたる。富士山麓特有の強風に苦しむ旅人と、それとは対照的に泰然と佇む富士の姿を輪郭線だけを用いて描いている。当の本人たちには気の毒だが、菅笠や懐紙が風に乗って飛ばされる様は、殊の外リズミカルで、この瞬間に居合わせた面白みを感じさせる。樹木が傾くほどの凄まじい風の動きと背景の富士とが見事なコントラストをなしている。(引用:東京富士美術館収蔵品データベース)